知識の無さを自覚した時にふと脳裏をよぎった「無知の知」という言葉。知っているようで正確に理解できていないと思い、ソクラテスに関する著作の中では最も有名であろう『ソクラテスの弁明』を読んでみた。
告発されたソクラテスが法廷で行った弁明の様子を、弟子(ソクラテスとしては友人と認識していたらしい)であるプラトンが書き表した作品となっている。
「無知の知」とは何なのか
本書の中にはソクラテスが「無知の知」を自覚するに至る話が書かれているので、それを自分の解釈を交えつつまとめてみる。
ある時、ソクラテスの友人であるカイレフォンはデルフォイで神託を受ける。その内容は「ソクラテス以上の賢者はいない」というものだった。そのことを聞いたソクラテスは頭を捻った。なぜならソクラテスは自分が決して賢くないことを自覚していたからだ。それなのに神は自分を「最も賢い」という。「きっとこれには何か意味があるはずだ」とソクラテスは考えた。
そこでソクラテスは市内にいる賢者と呼ばれる人たちのところに脚を運び、彼らと対話することにした。そんなことを繰り返しているうちに、ソクラテスはあることに気がついた。賢者たちは自分が最も賢いと信じてやまないが、ソクラテスから見るとそうではないように見える。彼らには知らないことがまだまだ多く、さして賢いようには思えなかったのである。
対話を繰り返すなかでソクラテスはこう結論づけた。“知らないことがあるのに、自分は全てを知っていると信じている人たち”よりも“知らないこともあるが、それを知っていると勘違いしていない”という点において、自分は彼らよりも賢明に思える。神が「ソクラテスこそ最も賢い」と言ったのは、どうやらその差のことなのだろうと。
以上がソクラテスが「無知の知」に至るエピソードである。勘違い賢者どもよりも、無知を自覚している自分のほうがまだまともじゃないかとソクラテスは悟ったわけである。
その後もソクラテスは神託の真偽を確かめるべく、賢者たちとの対話を続ける。そして賢者とは思えない人たちには「あなたは私から見ると全く賢者には見えませんけどね(ゲス顔)」と指摘することも行っていった。彼らに無知を自覚させることこそが神の意志なのではないかと考えたからだ。
しかし当然ながら、そんなことを繰り返していくうちにソクラテスは多くの人々から反感を買うことになってしまう。ついには告発されてしまい、法廷で行った「ソクラテスの弁明」に話は繋がっていく。
法廷でのソクラテスの姿に哲学を学ぶ
ソクラテスと言えば哲学の祖とも呼ばれる人物だが、彼が法廷で取った行動のひとつひとつからはその人生における哲学がにじみ出ており学ぶところは多い。
最終的にソクラテスは死刑判決を受けてしまうが、弁論の中でソクラテスは「自分が厚顔無恥であったならば、判決を覆すこともできた」と言いのける。多くの被告人のように泣きわめいたり、媚びへつらって哀願すれば死刑を避けることもできたというわけである。しかしソクラテスは「そのような恥辱を大衆の前で晒すぐらいなら」と潔く死刑判決を受け止める。
しかし私は、弁明の際にも身に迫る危険の故にいやしくも賤民らしく振る舞うべきではないと信じていたし、今でもそういう弁明の仕方をしたことを悔いない。むしろ私はかくの如き弁明の後に死ぬことを、そんなにまでして生きることよりも、遥かに優れりとする。
そして「有罪宣告をした人にも、告発した人にも、少しも憤りを感じていない」とまで言う。死刑を宣告されたその時までも、彼の毅然とした姿は一貫して崩れることはなかった。それはソクラテスの「善く生きる」という哲学がさせた態度なのだろう。
最も立派で最も容易なのは、他を圧伏させるのではなくて、出来得る限り善くなるように自ら心掛けることである。
この法廷にいた人物として、最も有名なのがプラトンである。ソクラテスのこの力強い弁論や生きる姿勢が、彼に多大な影響を与えたのは確かだろう。本書のなかで展開される筋道だった弁論やソクラテスの考え方などは、現代でも注目する価値が大いにあると言える。
50ページ程度の作品ではあるが、その内容は重厚である。また本書には脱獄を提案する友人クリトンとの対話からなる『クリトン』も収録されている。こちらも合わせて読むことで『ソクラテスの弁明』の深みも増すのでぜひ読んでみてほしい。
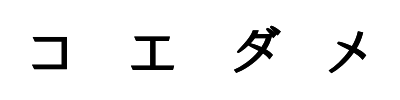




コメント