『金閣寺』は1950年(昭和25年)に起きた「金閣寺放火事件」を題材とした小説である。三島由紀夫の代表作であると同時に、日本文学史における傑作でもある。
内容としては事件当時に話題となった犯人の「動機」がメインテーマとなっている。犯人の供述は「世間を騒がせたかった」「社会への復讐のため」といった抽象的なものだった。それを三島由紀夫なりに解釈して敷衍したのが本書と言えるだろう。逆に言えばそれ以外の部分は実際の事件と共通する点が多い。例えば主人公が重度の吃音症だったこと、見習い僧侶だったこと、事件当日の鹿苑寺は火災報知器が壊れていたこと、などである。
「象徴」に火を放った主人公の心理
本書の注目すべきところは金閣寺に対する主人公の心理の変化だろう。主人公にとって金閣寺は美という概念の究極的な象徴であるわけだが、それに対する心理は複雑を極める。最初は絶対的な美に対する信仰のようなものであり、次第にそれが深い憧憬となり、終盤には憎悪に近いものへと変化していく。むしろ段階的に変化していったというわけではなく、これらの感情のすべてをひっくるめたものが主人公にとっての美だったと言うほうが正確かもしれない。
主人公がなぜ金閣寺を燃やしたか、というのは本書を読んでいくと容易にわかりそうでありながら、実際に考えてみるとなかなかに考えさせられる。とはいえその理由をまるまる一冊かけて書いた小説なわけなので、それを解釈することが『金閣寺』という作品を味わうことの肝となるはずだ。

まず主人公が金閣寺放火に至る兆候は第一章から随所に現れている。主人公は吃音症のために内界と外界の扉が閉ざされていると感じているわけだが、それにより「二種類の相反した権力意志」を抱えるに至った。一方は「暴君」であり、もう一方が「芸術家」である。この二種類の様態に憧れを抱いていたことは、その後の主人公の行動に大きく関わっていく。まず金閣寺の放火へと主人公を駆り立てさせたのは、まさにこの「暴君」としての破壊衝動によるものだろう。そして一方で金閣寺を究極の美として深く愛していたのが「芸術家」としての自分である。少年時代から主人公のなかには矛盾を帯びたふたつの意志が確かに存在していた。それは同じく第一章における海兵の生徒の短剣に傷をつけた行動にも見て取れる。美しい装飾がほどこされた短剣は自分を含めた中学生全員の憧れだった。その短剣に主人公は隙を伺って醜い傷をつける。美に対する破壊衝動はこの頃から主人公の内面に潜んでいたのである。
また金閣寺が空襲に見舞われることを願っていたこともその現れだろう。主人公は金閣寺と自分が同時に焼き尽くされるときが来れば、そのときこそ自身と金閣が同列の存在になると信じていた。そして結果的に空襲が来なかったことに絶望すら覚えている。これらの一連の行動を見ていくと、主人公が金閣寺放火という行動へ至ったのは当然の帰結のようにも思えてくる。
柏木の存在が主人公に与えた影響
文中でひときわ異彩を放つ存在が柏木だろう。柏木は内翻足という障碍を負いつつも、逆にそれを武器として上流の女性をもてあそぶという一周回って魅力的な人物である。彼の魔性を帯びた言葉の数々が主人公の悪の側面を助長したのは間違いない。ただ正確には柏木独特の悪性に触れることにより、主人公の内なる悪が浮き彫りになったと言うべきだろう。

このふたりの共通する点として生を耐えがたきものとして捉えていることがある。しかし異なるのはその耐えがたさを変貌させるための考え方である。柏木は耐えがたき生を「認識」によって変えようとしてきた。内翻足を足かせとは考えず、反対に内翻足こそが自身を定義する象徴的なものと考える。つまり自身の認識を変化させることにより、目の前の世界を変えようとしているのである。
内翻足が俺の生の、条件であり、理由であり、目的であり、理想であり、……生それ自身なのだから。
一方で主人公は「行為」こそが生を耐える方法だと考える。思えば作中で描かれる主人公像としては行為が先んじている印象が強い。短剣に傷をつけたとき、有為子の眼前に躍り出たとき、外人の妊婦の腹を踏み潰したとき、老師の新聞に芸妓の写真を紛れ込ませたとき、金閣寺を燃やしたとき……。
「世界を変貌させるのは行為なんだ。それだけしかない」
これは主人公が吃音症であることに関係があると考える。幼少期から吃りによって言いたいことを上手く言えず外界と内界が閉ざされてきた主人公は、その鬱積によっていつしか「行為」そのものを神格化するに至ったのではないだろうか。言い方を変えれば、主人公は行為によってしか世界と向き合うことができなかったのかもしれない。
三島由紀夫の大胆な告白
三島由紀夫は事件を題材にすることで、自らが抱く「美」や「行為」といった観念に一定の答えを出したかったのではないかと思う。作中で展開される主人公と柏木のやり取りは弁証法的にそれらを導きだそうとしているように感じた。巻末解説で中村光夫が『金閣寺』を三島由紀夫の「大胆率直な告白」と表現しているが同意見である。また当時は戦後ということで、坂口安吾の『堕落論』などでも書かれているように国内には鬱屈した空気が充満していたのだろう。その最中で起きたこの衝撃的な事件をモチーフとした小説を書くことで、当時の日本人の精神を解剖しようとしたのかもしれない。
また『金閣寺』の精緻な文体が森鴎外を参考にして作られたというのも興味深い。最近になって発見された三島由紀夫の肉声テープで「小説は思想ではなく言葉を素材として作られる」ということを言っており感銘を受けたのだが、この作品も良い意味で人工的な美しさを持つ文章となっている。文章が美しい作家の筆頭としてあげられる三島由紀夫の文章にどっぷりと浸れることができるのもこの小説の魅力だろう。
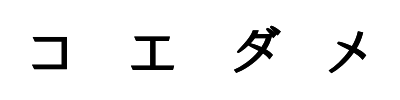



コメント