安部公房といえば『メタルギア』シリーズの生みの親である小島秀夫氏の話を思い出す。彼によればダンボールを使って身を隠すというあの常軌を逸した行為は、安部公房の『箱男』をモチーフにして生まれたらしい。それを知っていたのもあって安部公房を読むならまず『箱男』が読みたかったのだが、古本屋を漁っていたら『砂の女』が100円で売っていたので先に手を出すことになってしまった。この記事を書くまでのくだらない経緯はこんな感じ。
とはいえ文学的評価については『砂の女』は凄まじいものがある。二十数カ国で翻訳され、フランスでは最優秀外国文学賞を獲得するなど、安部公房の名を世界に知らしめた作品と言える。しばしば日本文学史上における最高傑作と評されているのも見かけるが、前述のとおり自分は安部公房の小説を読むのがそもそも初めてなのでそれが正しいかどうかは知る由もない。ただ一読しただけでも日本文学のなかで安部公房がかなり特異的な位置に存在するのは理解できた。『砂の女』の不条理でありミステリアスでありエロティックでありサスペンスであり、それでいて底知れないものを感じさせる世界観に触れると、国内外を問わず広く評価されているのも納得してしまう。
あらすじとストーリーのポイント
主人公の仁木順平は昆虫採集のために砂丘に出かけたが、そこで砂穴の底に埋もれる家に閉じ込められてしまう。当然ながら主人公はあの手この手でそこから逃げ出そうとするのだが、穴に流れ込む砂によってそれは不可能となっている。家のなかには夫と子を亡くした女がいるのだが、家を守っていくためには男手が必要ということで主人公を引き止めようとする。穴の外には部落があり定期的に村人が物資を届けにやってくるのだが、彼らは男からの「外に出たい」という要求にまるで聞く耳を持たない。そんな異常な状況が基盤となっているのがこの小説である。

ここでまず注目すべきは主人公と女の考え方の違いである。砂の底にある家の暮らしは過酷を極める。食事は傘をさしていないと砂が降ってきて食べられたものではないし、寝て起きるだけでうっすらと砂が体に積もる。また家自体も放っておけば砂に埋もれてしまうので、毎日欠かさず砂を穴の外へかき出さないといけない(かき出した砂の運搬は部落の人びとがやってくれる)。都市での生活に慣れている主人公にとってこのような劣悪な環境は耐え難いし、なにより彼には教師としての仕事がある。だからこそ主人公はなんとしても脱出したい。では女も同じように考えているかというとむしろ逆で、女にとってはこの家を守ることが生きがいになっている。労働に従事していれば最低限の食料は手に入るし、主人公が来たことによって生活に余力が生まれたので内職をして貯金をすることもできるようになった。そのお金でラジオを買おうとウキウキしているぐらいだ。
興味深いのはこれだけ主人公が求めてやまない外界の生活が、実はまったくもって希望に満ちていないことだ。小説のなかではときどき主人公の外での生活が回想されているが、妻とはうまくいっていないし、同僚とも妬み嫉みの関係らしく、明るい要素はまるで見当たらない。そんな主人公の生きがいは昆虫採集だった。彼は新種の昆虫を発見し、その学名に自分の名前が使われる名声を夢見ている。その生きがいが無ければ彼には灰色の日常しか待っていないのである。
ラストにおける主人公の選択の意味
最終的に脱出の機会を得た主人公だったが、選択したのは「穴のなかに残ること」だった。主人公は「希望」という桶状のカラス捕りを仕掛けていたのだが、ある日その桶のなかに水が溜まっていることに気がつく。この地の特殊な砂が罠の構造にたまたま合致して溜水装置の役割を果たしたのだった。連日その装置の研究を続けていくうちに、気がつけばこの装置が自分にとって生きがいとなっていることに気がつく。もともと昆虫採集をしていたのもくだらない日常に「名声」という潤いを求めていたからだった。ここには自分が心血を注げる研究対象があり、それを確実に評価してくれる人──部落の人びとや女──がいる。今や主人公が元の生活に戻る意味は消失していた。
それに、考えてみれば、彼の心は、溜水装置のことを誰かに話したいという欲望で、はちきれそうになっていた。話すとなれば、ここの部落のもの以上の聞き手は、まずありえまい。
日に日に新聞への興味を失っていく描写にもそれが現れている。当初はあまりに味気ない砂の生活に新聞を熱望していた主人公だったが、最終的には新聞の存在すら忘れている。主人公にとって外の世界はやはり無意味なものになったのである。

主人公のこの心情の変化は題辞として書かれている「罰がなければ、逃げるたのしみもない」という言葉に集約されている。「罰」とは主人公にとっては「砂のなかでの生活」であるはずだった。しかし実際には外界には自分が戻るべき理由などそもそもなく、逆にあれだけ逃げ出したいと思っていた場所にこそ潤いが存在した。「逃げるたのしみ」などあるべくもない。
作品の主題はなにか
この不思議な小説の主題はなんなのだろうか。安部公房本人の言葉を踏まえて考えてみると、個人的にはこの小説は「自由」という概念を明確にしようと試みたのではないかと思っている。実際に安部公房もそのようなことを言及していたようだ。
鳥のように、飛び立ちたいと願う自由もあれば、巣ごもって、誰からも邪魔されまいと願う自由もある。飛砂におそわれ、埋もれていく、ある貧しい海辺の村にとらえられた一人の男が、村の女と、砂掻きの仕事から、いかにして脱出をなしえたか──色も、匂いもない、砂との闘いを通じて、その二つの自由の関係を追求してみたのが、この作品である。砂を舐めてみなければ、おそらく希望の味も分るまい。
— 安部公房「著者の言葉──『砂の女』」
砂の女 - Wikipedia
砂丘に来るまでは主人公にとっての自由とは外の生活にこそあるはずだった。しかし不自由であるはずの砂穴の底で生活する女は、そこに生きがいを見出している限りなく自由な存在だった。この両者を対比させ、そして主人公が個人的な自由に目覚めていく過程を見ることで「自由」という概念を浮き彫りにさせようとしたのではないか。
『砂の女』を読んだ後にこうして考えてみても「何が自由なのか」というのは答えを出しにくい問題だ。そういった不確かさ、とらえどころのなさが「砂」という題材を安部公房に選択させたのだろう。作中で何度も言及されているように砂は流れては定着し、また流れていくの繰り返しである。「流動そのものが砂なのだ」とは小説のなかでの主人公の言葉だが、これはそのまま自由という言葉にも当てはまらないだろうか。人、時間、場所によって自由という概念は常に流動し、とらえどころがないのである。
他にもこの小説の見どころとして、いきなり主人公の行方不明による死亡認定から始まる冒頭や死亡の審判書で終わるラストなどの劇的な表現、現在から過去まで限りなくシームレスな情景描写、エロティックで美しい性描写など枚挙にいとまがない。だからこそ世界的に評価されている小説なのだと納得させられる。
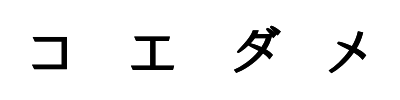




コメント