主題だけだとこの本が何を言いたいのか全くわからないが、さすがにその点は著者も気がついたのか副題がかなり核心を付いたものになっている。つまり読書が脳にどのような影響を与えるのかを解き明かしていくのが本書の内容だ。インターネットが全盛の現代において人間が読書をする時間は年々減っている。それだけに読書の大切さが謳われることも多いが、その具体的な効用にまで深く言及している媒体はほとんど見られない。
本書では「ディスクレシア(読字に障がいを持つ人のこと)」と一般的な読字能力を持つ人とを比較しながら、人間が文字を読み進める過程でどういった能力を獲得しているのかを解き明かしていく。興味深いのは読書をすることによって実際に脳の構造に変化があらわれるということだ。情動や思想の面で変化を与えるのは予想できるとして、読書という行為が人間を細胞レベルで変化させるような力を持っていることには素直に驚かされる。
この記事では「読書が人間をどのように変えるのか」といったことに加え、読書をしない代わりに時間を費やす事象の代表であるインターネットによって人間は何かを失うのか、ということについてまとめていきたいと思う。
読書は人間をどのように変えるのか
読書が我々に何を与え、何を変化させるのかということに興味を持つ人は多いだろう。本書では読書という行為によって生じる影響を、感情から脳の構造まで、様々な側面から取り上げている。
著者は人は読書体験によって人間の考え方に共通性と独自性があることを認知できると述べる。読書をするとき、人はそこに書かれている内容に共感して安心したりするし、また自分とまったく違う考え方に触れることで驚いたりもする。それはまるで他人の意識に入り込んでいるかのようだ。その体験によって世界にはさまざまな考え方をする人がいることを知り、自身を客観的に見ることができる。これは子どもが絵本を読む時でも大人が難解な古典を読む時でも共通だ。これが読書の効用のひとつである。
こうして他人の意識を直接体験することにより、私たちは自分の考え方に共通性と独自性があることを悟る──自分は一個の人間であるけれど、一人きりで生きているわけではない、そう悟るのである。
またそういった思想形成のような側面だけでなく、読書は実際に脳の構造に変化を与える。詳しく言えば、脳を構成する神経細胞である「ニューロン」に変化が起こる。繰り返し文字を読むことにより、脳はどのように動けばスムーズに読書ができるかを学んでいく。素早く文章を読み解くための新しいニューロンが生成されたり、また読書に必要のないニューロンはあえて動かさなくしたりと、より読書に適した脳の構造に成長していく。負荷をかければ大きくなる筋肉のようなものと捉えることもできるだろう。
つまり、読字が熟達のレベルに達すると、ニューロンのレベルで変化が起こるのだ。

本を読み慣れていない人と読書が習慣づいている人とは一冊を読むまでのスピードに大きな差が生まれる。これは読むテクニックが原因ではなく、単純に脳の構造が違うからだ。長いあいだ本を読んできた人は、それだけ読字行為に対して最適化された脳構造を持っている。これは言い換えれば、読書を繰り返していくことで人は誰でも本を素早く読めるようになるということだ。「本を読むのが苦手」という人は多いが、そういう人でも少しずつでも活字に触れていくことで確実に脳に変化が起こり、読書能力は上がっていく。この事実は人を読書に駆り立てるのに十分な力を内包しているのではないだろうか。
インターネットの登場で何かを失うのか
「インターネットによって人は何かしらの能力を失うのか」ということについてだが、これはいまだに研究段階であり、現状では明確な答えが出せない難しい課題であるそうだ。インターネットの進化は著しいが、その歴史はまだ浅い。解明にはまだまだ時間がかかるのだろう。
たとえば、ブラウザの“戻る”のボタンやURL構文、“クッキー”といったツールがあるが、これを使用することが認知スキルにどのような影響をおよぼすかという研究はいまだ緒についたばかりだ。
しかしながらインターネットによって人々は本を読む時間が減った。それにより育まれるべき読字能力は低下の一途を辿っている。これは確かに事実ではあるのだが、だからといってインターネットを規制するべきという結論に至るのも危険だろう。悪い面ばかりを見てしまいがちだが、インターネットによって我々が多大なる恩恵を得ているのも事実だからだ。

この問題に対する著者の答えは実にシンプルで、「両方の良いところを採用すればいい」である。拍子抜けな結論ではあるが、確かにその通りだと思う。著者が危惧しているのは将来の人々が「本か、ネットか」というように、それらを二者択一の選択肢にかけてしまうことだ。そうなった時点でどちらかを切り捨てることになってしまい、進歩の道は閉ざされてしまう。それは建設的では決してない。読書によって脳に変化が起きたことからわかるように、我々の脳は持ち主の行動によって構造を変化させ、あらゆる物事に順応することができるのである。それならば「本か、ネットか」ではなく、「本も、ネットも」というように良いところ取りをするのが最も適切と言えるだろう。
私たちの後を継ぐ世代には、いったん足を止めて、最も優れた熟考する能力を働かせ、思いのままにあらゆるものを駆使して、来るべきものの形成に備える機会がある。それをとらえさえすればよいのだ。分析と推論ができ、自分の考え方で文字を読む脳に、人間の意識を形成するあらゆる能力と、敏捷、多機能、視聴覚を含む複数のコミュニケーション・モードを利用するマルチモーダル、情報統合を特徴とするデジタル思考の能力が備われば、排他的な世界に住み着く必要はない。
ソクラテスは対話を重視して、書き言葉を徹底的に嫌った。書き言葉はさも真実のように見えるし、反論も許さない。「人間とは何か」を徹底的に追求するソクラテスにとって文字や文章といったものは非常に危なっかしい存在に見えたのだろう。そんなソクラテスの態度は現代の我々からすれば病的なまでの過剰反応に見えてしまうが、著者からすればそれはちょうど我々がインターネットに対して危惧していることと同じだと述べる。
ただ幸いなことにソクラテスの予想は誤っていた。実際には書き言葉はソクラテスが最善とする「対話」をひとりの人間の中で再現できる素晴らしい発明だったのである。そして本だけでなくインターネットも書き言葉で構成されているという点で同じ側面があることを忘れてはいけない。著者が言うように、人間にとって大切なのは何かを切り捨てるという選択ではなく、それらを組み合わせてより高次の段階に進む道を模索することなのである。
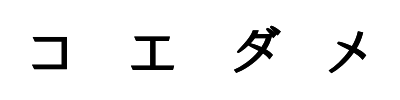




コメント