当ブログでもたまに書評記事を書くが、これがなかなか難しい。「本を読んで感想を書く」というだけのことなのだが実際はそれほど単純ではなく、要旨を切り抜く能力が求められるし、そこに独自の解釈も加えなければいけない。そうでなければ単なる要約に終始してしまうからだ。この本の面白さを伝えたい。それなのに言葉がうまく出てこない。文章がまとまらない。そんなときの息苦しさは筆舌に尽くしがたく、記事自体を葬り去って無かったことにした日も少なくはない。
こういうときは手っ取り早くその分野の達人から学ぶに限る。自分のなかで「書評の達人」として思い浮かぶのは「丸谷才一」だ。丸谷才一の膨大な知識から繰り出される軽妙な評論が好きなのだが、そのなかでひときわ熱量を感じたのが書評について語っている箇所である。実際に彼が日本の書評に与えた影響は大きく、「近代日本資本主義の父」が渋沢栄一なら「近代日本書評の父」は丸谷才一だと言っても過言ではないだろう。
丸谷才一の書評集は何冊も存在するが、そのなかで今の悩みに合いそうなのが2005年に刊行された『いろんな色のインクで』だった。大半が書評を占める本書だが、第一章「書評のレッスン」では丸谷才一が対談形式で書評の必要条件について語っている。この章に書かれている内容を自分なりに噛み砕いていきたい。
書評に必要な三要素
丸谷才一(以下「著者」)は書評において大事なことを3つ挙げている。
- 本の選び方
- 筋の要約と批評
- 藝と趣向の必要
まず「本の選び方」についてだが、著者は「自分の内部にいる読者を大事にする」ことを心がけているという。自身の心に従い純粋に読みたい本を選ぶ。売れ筋や話題になっている本を選んだほうが多くの人の目には付くかもしれない。ただそれでも自分の読みたいものを同じように読みたいと思っている人もそれなりの数はいるだろうし、そうしたほうがより情熱を注げられるので良い文章が書けるだろう。
近頃はこの傾向が流行ってるとか、どういう本が売れたとか、何が最近は評判が悪いとか、そういうことは考えないで、ただ自分の心の中だけを見つめる。僕が本当に読みたいと思うものを読みたいと思う人は、いまの日本にまあ五千人はいるんじゃないか。ひょっとすると一万人ぐらいいるんじゃないか。いや、ひょっとすると、もっと多いんじゃないか。そういう考え方をするんですね。
「筋の要約と批評」はそのままの意味だ。本を書く人からすれば複雑な心境になるかもしれないが、書評の機能は「実際に読まない人でも、一応それを読めば間に合う」ことだと述べられている。もちろんそれは単なる要約に終始すればいいという話ではない。そこに評論が加わって初めて書評としての形をなすことは忘れてはいけないだろう。
とにかく、普通の人がその本を知るための要約と紹介、それが第二です。もちろんそれにはおのずから、評価が含まれることになるでしょう。
そして第三が「藝と趣向の必要」だが、実は著者の「書評のレッスン」はこの部分に集約される。というのはここまでに取り上げてきた要素も究極的には藝と趣向が求められているからだ。本を選ぶのにも、評価をするのにも、そこには少なからず遊び心や洒落っ気のようなものが必要だ。それが書評を書く人間の個性となり、読者がその書評を読む意味になる。これらの三要素は段階的に高度になっており、それと同時にこれらを余すことなく表現できたときに素晴らしい書評が生まれるというのが著者の主張だ。
第三として、書評を書く人間の藝とか語り口とか、そういうものを面白がるということがありますね。これがいちばん高度な段階なわけです。この三つがあって、この三つのことが渾然と一体になったときにいい書評ができるわけです。
藝を凝らした書評とは
では「藝、趣向、語り口」といったものを発揮した書評とはどういったものなのだろうか。あまり具体的には書かれていないが、そのヒントとなることは本書ではいくつか紹介されている。
まず前提として書評には敵が多いということを忘れてはならない。こういった個人ブログはまだしも、新聞や週刊誌に載るような書評はセンセーショナルなニュースや目を引くような広告に競り勝ち、自分の記事を読み続けさせなければならない。そのために必要なのが「藝、趣向、語り口」であるという話に再び繋がっていくのだが、とりわけ「最初の何行か」で人を惹き付けるような工夫が求められると著者は述べている。
そのためにも、藝、趣向、語り口が大事ですね。殊に最初の何行かは腕の見せどころでしょう。
「書評というのは、ひとりの本好きが、本好きの友だちに出す手紙みたいなもの」という言葉も含蓄に富んでいる。見ず知らずの人間相手に自分の文章を読ませ、さらにその本の良し悪しを理解してもらうのが書評だ。そうするためには文章を通じて信頼関係を築く必要がある。魅力的な考え方をしている、面白いことを言っている、と思われなければならない。これは単にフランクな文章を書くという意味ではなく、より根本的な部分への指摘であるように思う。
こうして見ていくと書評というのは文字どおり本の評論ではあるものの、そこには書き手の人間的な部分が入り込む余地が多く、想像以上に自由な表現が許される場所なのだと気付かされる。書評において対象の本を正しく、深く理解するということは大切だが、それと同じぐらいに書き手の人間力も重要となるのかもしれない。
おわりに
本書のなかで対象として語られているのは職業としての書評家についてであり、ブログで本の感想を書く程度の自分からすると高尚な内容が多いというのが正直なところだ。ただそういったなかにもやはりヒントになる部分は多く、自分が書評について抱いていた疑問や迷いの多くが氷解されたように思う。特に「自分の心に従った本を選べばいい」という内容の意見には安心感を覚えた。
この記事で取り上げたのは本書のなかの20数ページだけの内容だ。これ以外にも書評やエッセイなどが数多く収録されており、ここには丸谷才一の執筆活動のエッセンスが詰まっている。本書は娯楽として楽しむことができるのはもちろんだが、個人的には文章における論理の構築や言葉選び、そして欠如しがちなユーモアを学ぶための本として読み解いていきたい。
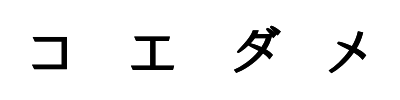




コメント