80歳くらいまで生きるとして、あなたの人生は、たった4000週間だ。
そんなゾッとするイントロダクションから本書は始まる。「4000週間」という時間をどのように捉えるかは人によるだろうが、ほとんどの人は考えるほどに短すぎるものに感じるのではないだろうか。
ただ注意したいのが本書の主旨は「短すぎる人生だから効率よく計画的に生きよう」というようなものではない。著者が語っているように本書が執筆されたのは「従来のタイムマネジメントのアドバイスがあまりにも近視眼的なものだったから」という経緯があったからだ。そのため内容としては「方法論」や「時間管理術」といったありがちなものではなく、言わば「時間に対する向き合い方の提案」といった本質的なものになっている。
未来に備えるために「今」を軽視する人たち
昔と比べると本を読めなくなった、というのは自分だけではないと思う。本が好きなのは間違いない。ただ最初の1ページを開くのに恐ろしく時間がかかるし、ようやく開いても数分後には閉じて別のことをやっている。
「時間」が題材ということもあって本書では上記のような人々にも言及されているのだが、著者はそのような状態に陥る原因が「焦燥感」にあると述べている。
ここ10年ほど、本を読もうとするたびに「没頭できない」「気が散って仕方ない」と強く感じる人が増えてきた。この感覚も、実は一種の焦燥感だ。読書という時間がかかる行為に対して、「もっと早く終わればいいのに」という不満をどこかで感じているのだ。
「本から学びを得たい」「ブログに感想を書きたい」と思って読んでいるのに、残りのページは一向に減ることはない。そんなときに人は焦燥感を感じ、「さっさと終われ」と思ってしまうのだろう。あまりにも傲慢だが、そういった例は何も読書だけに限らずあらゆる場面において存在するように思う。そして実はその感覚こそが本書のテーマのひとつだったりする。
本書の中で著者が繰り返し問題点として指摘しているのは、時間をコントロールできるものと勘違いしている現代人の傲慢さだ。現代の人々がそのような考え方をしてしまうのは、遡れば時計の発明に端を発するらしい。時計によって流動的だった時間に区切りが設けられ、また産業革命によって時間に値段が付けられるようになった。そうして文明を発展させてきただけに、次第に人類は「時間は支配できるものだ」と思うに至った。もちろんそうして便利になったものは数知れない。ただその一方で、人間は「手間がかからない」ということに慣れすぎてしまい、最も大切なはずの「今」を軽視するようになってしまったというのが著者の指摘だ。
永遠の先延ばし
読書に話を戻せば、子供の頃の自分にとって本を読むことはただそれだけで楽しいものだったはずで、そこに見返りのようなものは決して求めていなかった。極めて神聖な時間だったはずだ。
本来はそれこそが正しい読書体験なのだろうが、今の自分にとって読書は別の目的に至る通過点のようなものになってしまっている。著者の言い方をすれば、それは行動にあてる時間を「道具」や「手段」とする見方だ。こういった態度の危険な点は、大切な「今」を未来への準備として使ってしまうことにある。本来なら最も重視するべき「今」という時間を、来るかどうかもわからない未来のために先延ばしにしてしまうのである。
そういう未来志向の態度は、「いつか何かをしたら」という考え方にもつながりやすい。「いつか仕事が落ち着いたら」「いつか素敵な人に出会ったら」「いつか心理的な問題が解決したら」、そのとき初めてリラックスして、本当の人生を生きられるというわけだ。
(中略)でもそんな考え方をしていたら、いつまでたっても満たされることなんてない。なぜならそれは、現在を永遠に先延ばしにする考え方だからだ。たとえ仕事が落ち着いても、たとえ素敵な人に出会っても、そのときはまた充実感を先延ばしにするための別の理由がいくらでも見つかることだろう。
重たい言葉に具合が悪くなってきそうだが、まさにこのような心理状態が現代には蔓延っているのではないだろうか。言うまでもなく、大切なのはいま目の前にある体験そのものである。そこに目を背け、いつか来る未来のために「今」を浪費すれば、現在の体験すべては味気ないものになるだろう。むしろすでにそうなりはじめているのかもしれない。だからこそ次なる「やるべきこと」を用意して、大切な現在を先延ばしにする。恐ろしき無限ループの完成だ。
深い時間を生きる
未来に囚われず、「今」とただひたすらに向き合う神聖な時間。本書の中ではそれが「深い時間を生きる」と表現されている。例えば中世の人々はそのような時間の中を生きてきたそうだ。時計すらない時代の彼らの生活は不便極まりないだろうが、著者は時間という観点では「今より恵まれていた」と述べている。
どんなに農作業が忙しい時期でも、「やるべきことが多すぎる」「もっと急がなければ」「時間が飛ぶように過ぎてしまう」という問題はなかったし、ワークライフバランスに頭を悩ませる必要もなかった。逆に余裕のある日にも、「退屈だ」「何かやらなくては」などと焦る必要はなかった。つねに死と隣り合わせで、今よりずっと寿命が短かったにもかかわらず、人々は「時間が足りない」と感じていなかったのだ。
また赤ちゃんもそのような存在として登場する。「退屈だ」「何かやらなくては」と現実逃避することは当然ない。ただ全力でこの瞬間を生きているだけだ。そういう点では野生動物にもそういった美しさがあると言えるだろう。
ただ我々は中世時代はおろか、赤ちゃんにだって戻ることはできない。「今を生きる」ということは考えるほどに難しいことに思えてきてしまう。本書でも述べられているように、そもそも自分たちを取り巻く資本主義が時間を手段や道具として扱うことで利益を生む構造なのである。そんな中に生きていれば、「時間との向き合い方を変えろ」と急に言われても困惑するのは無理もないのかもしれない。
本書の中でもついには「今を生きる」ための具体的な方法は語られなかったが、おそらくそれは自分で到達しなければ意味のないことなのだろう。幸いにも本書には章や巻末付録に読者の思考を促すための質問やツールが多数用意されているので事欠くことはないだろう。
おわりに
本書のメッセージは冒頭から末尾まで一貫しており、それは「時間をコントロールできるという驕りを捨て、自分の限界を認めよ」というものだ。人が時間について悩むのは、その前提に「時間を完璧にコントロールできる理想の自分」を思い描いているからだ。しかし現実はそうではない。やりたいことをすべてやるのなんて無理だし、読書をするのには時間がかかるし、人生はおそろしいほどに短い。
夢のない話だが、その「不愉快な現実」を受け止めることは、そこから目を背けるよりは余程ましだ。現実逃避をし続ければやりたいことが多すぎて脳がパンクするだろうし、読書をしたいのに本が読めなくなり、人生はまだこれからと思ううちに死んでしまう。
この不愉快な現実は、しかし、自由への一歩だ。幻想にしがみつくことをやめて、現実をしっかりと見つめたとき、そこに現れるのは無力さではなく、あふれんばかりの活力だ。
自分たちの持つ「時間」という概念を抉ってくるだけに、本書の内容を真正面から受け止めるのには簡単ではないが、だからこそ読むことに価値があると言える。自分も最初はあまりピンと来ないまま読み進めていたが、次第に色々と考えさせられることとなった。この記事で引用した内容は本書の極一部にすぎないので、興味があれば手にとってみてほしい。
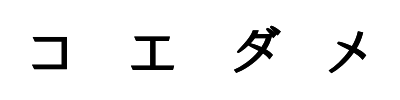




コメント
「いつか…」はよく口にするから自分の話をされているみたいでかなり興味深かった。