例えばAIに「イチゴは甘酸っぱくて美味しい」と覚えさせるとする。次からAIはイチゴを見聞きしたら「甘酸っぱくて美味しいもの」と認識するだろう。ただ人間と違い、AIは実際にイチゴを食べた経験があるわけではない。そのときAIは本当にイチゴについて「知っている」と言えるのだろうか?
上記は認知科学で「記号接地問題」と呼ばれているものである。この問題では、やはりAIは「イチゴ」という記号を他の言葉と関連付けて説明はできても、それは表面的な処理に他ならないと結論付けられている。それが五感を持つ人間との大きな隔たりとして、AI分野に長らく立ちはだかっているそうだ。これは逆に言えば、人が言語を理解するには身体を通した感覚や経験が不可欠だとも言えるだろう。
ただそうなると生じるのが、人間は最初にどのようにして言語を習得するのかという問いだ。聞いたこともない外国語を、辞書もなしに習得することを想像してみてほしい。途方も無いことのように思えるが、実際に人間の赤ちゃんはそのような状況を乗り越え、言語を操るに至っている。生まれたての人間が、最初の言葉を覚えるきっかけとは、一体何なのだろうか。そしてそこからどのように語彙を増やしていくのだろうか。
本書は「記号接地問題」をスタートラインとして、「オノマトペ」や「推論」といった側面から人間が言語をどのように習得しているかを考察している。我々の言語習得までの壮大な旅路を紐解く一冊だと言っていいだろう。
身体と言語を繋ぐオノマトペ
まず本書では、人の言語習得に大きく貢献するのが「オノマトペ」だとされている。記号接地問題における「言語は身体につながっている」という定義が正しいとして、オノマトペは言語と身体をつなぐ架け橋のような役割を果たすからである。
以下の図形を見て、どちらが「キビ」で、どちらが「モマ」と思うだろうか。おそらくほとんどの人は左を「キビ」、右を「モマ」と感じることだろう。実はこの感覚は日本語話者だけの感覚ではなく、世界中の言語話者でも共通の感覚であるらしい。そしてそう感じるのはなにも大人だけではなく、生まれたての赤ちゃんでも例外ではないそうだ。

つまり人間は生まれたときから「音」がどの対象を指し示しているのかを感覚で識別しているのである。本書ではこの共通の感覚が、言葉と身体経験をつなぐ最初の一歩になるのではないかと推測している。
一般的な言葉と異なり、オノマトペは単語の音と意味がつながっている。例えば「犬」という言葉を赤ちゃんが初めて聞いたとき、それだけでは何を指すのかを推察することはできないだろう。しかし「ワンワン」の場合はどうだろうか。これは犬の鳴き声でありながら、犬そのものというニュアンスでも使われている。これにより赤ちゃんは「ワンワン」という言葉は、今そこで同じように鳴いている犬のことなのかもしれない、と推察できるのである。
オノマトペの役割を、本書では「子どもに言語の大局観を与える」と表現されている。言語習得という途方もない旅に出る赤ちゃんに対し、オノマトペはその背中を押す重要な役割を果たしていると言えるだろう。
オノマトペの弱点
ただ当然ながらオノマトペにも弱点はある。一般的に赤ちゃんの言語習得はオノマトペが効果的な入口にはなるものの、次第にそこから離れて一般語へと移っていく。そもそもオノマトペが多いと言われる日本語ですら、オノマトペは語位全体の1%程度であるそうだ。そこにはオノマトペ以外の言葉を使用せざるを得ない理由がある。
ひとつは語彙を増やす上で、言葉同士を組み合わせることが重要となっていくからだ。本書では「転がる」「落ちる」という言葉が組み合わさり、「転がり落ちる」という語彙を得るプロセスが紹介されている。単純なようだが、こうして単語を組み合わせて表現しなければ、人間は未知の事象すべてに対していちいち別の単語を用意し、覚えなければならなくなる。既存の概念をベースに物事を理解することで、人間は無駄な労力を必要とせず言語を習得していくのだろう。そしてこれは「感覚イメージをそのまま写し取る」という性質のオノマトペが苦手とする分野だとも言える。

もうひとつは情報処理においてオノマトペは不利になることが多いという点だ。例えば先ほどの例であれば「ワンワン」というオノマトペは赤ちゃんに「犬」という存在を認知させるうえで効果的だった。しかし沢山の種類の犬を前にしたとき「ワンワン」ではどれのことを言っているのかが説明できない。説明のためにはすべての犬の鳴き方を完璧に模倣しなければいけないだろう。しかしそのような労力をかけるぐらいなら、「大きい犬」「茶色い犬」といった説明をするほうが簡単だろうし、もしくは犬種名を暗記するほうが効果的だろう。
つまりオノマトペは子どもの言語学習の足がかりにはなるものの、語彙が増えるにつれて、かえってその足を引っ張る。オノマトペによって理解した概念を子どもは分解し、結合し、新たな語彙を得ていく。そしてそれらの語彙は既存の概念をベースにしているからこそ、実際に体験していなくても身体の一部であるような感覚を持つことに至ると言われている。
子どもが「練乳」を「しょうゆ」と間違う理由
最後に本書では子供がオノマトペから離れ、この膨大な言語をどのようにして習得していくかという具体的な方法についても言及されている。そしてその方法として挙げられているのが「アブダクション推論」だ。
アブダクション推論は「仮説形成推論」のことで、ざっくり言えば仮説に基づいた推論のことである。あくまで仮説であるため、これは演繹推論などとは異なり、常に正しい答えを導くことはできない。そのため子供はアブダクション推論を用いて以下のような間違いをときおりするそうだ。
- イチゴのしょうゆ
- 足で投げる
①は「練乳」のことである。この間違いをした子は“食べ物にかけるもの”はすべて「しょうゆ」なのだと勘違いしたのだろう。②はボールが飛ぶという事象はすべて「投げる」ことによって起きると考えたに違いない。子どもにこういった間違いが実に多いことは、思い当たる人も多いのではないだろうか。
実はこのプロセスこそが言語習得において重要な役割を果たしている。先ほどの例で言えば、子どもはまず「練乳」と「しょうゆ」の共通点を見出している。そして“食べ物にかけるもの=しょうゆなのではないか?”という仮説を自分なりに立て、日常のなかで用いていく。そして仮説が合っていれば問題ない。では間違っていたら? なんのことはない。子どもは誤った仮説を修正し、次の学習に役立てていくのである。
こうして見ると、アブダクション推論は実践のなかから言語を習得していくプロセスに思う。そして実践的だからこそ、身体に根付いていくという側面もあるのかもしれない。個人的には一般によく見かける子どもの言い間違いや勘違いという行為が、実は高度な学習のプロセスであることに少なからず感動を覚えた。間違いを恐れがちな大人にとって、子どものこの言語習得の過程には勇気づけられる思いだ。
新書でありながら重厚な内容の一冊だ。ただ我々が一生付き合っていく言語について理解を深めることは、得られるものも多いはずである。気になったら手にとってほしい。
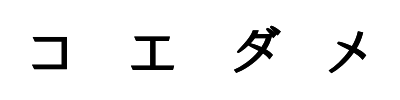




コメント